| 日 時 | : | 平成23年8月15日(月) 13:00頃~ |
| お客様 | : | 台湾出身の友人 |
1年前から、ヤン先生の中国茶芸教室に通い始めました。
そのきっかけを作ってくれたのが、この日招いたお客様です。
私は、彼女が子供の通っていた保育園の先生をしていて、知り合いました。
気さくに話しかけてくれ、子供の様子を親切に教えてくれる女性でした。
そんな優しい人柄に惹かれ、子供が卒園してからもずっとお付き合いしていました。
数年前、彼女の家に遊びに行った時、何のこだわりなく普通に、おいしいお茶をいただきました。
これが、私の中国茶器と中国茶との出会いです。
それが今まで飲んだことの無い種類のお茶だったことと、おままごとのような可愛い茶器だったことがとても印象に残っています。
ずっと、なかなか子供が手から離れなかったのですが、やっとゆっくりとお茶を飲める時間ができるようになったので、
ヤン先生の茶芸教室の門をたたいたのです。
一年経って、「お茶会をやってみたい」、そしてお茶会をやるなら「初めてのお客様は彼女に」と決めていました。
当日、
「歡迎、歡迎。」 (huānyíng, huānyíng)
|
1.昼食メニュー
・水餃子
・骨付き鶏肉と大根のスープ
・ツナとひじきのサラダ
・ほうれんそうのにんにく炒め
・冷やしたプーアール茶
パッケージには、「沱茶」と書いてあったので、勉強不足の私は、お茶の種類かと思っていました。
沱茶は、プーアール茶のうち、形状が固形茶の中のお碗型に堅圧形成したものであることが後でわかりました。
昼食は、肉料理が多かったのと、その日はまだまだ暑い日だったので、お茶には、冷蔵庫で冷やしたプーアール茶にしました。
メニューの水餃子は、以前ヤン先生の料理教室で作ったものです。
「餃子と言えば、焼き餃子」→「水餃子はスープ餃子」→「餃子にはご飯」と思っていた今までの概念が崩れた一日でした。
中国では、「餃子は水餃子が一般的、湯通しした餃子をたれでご飯としていただく」というのが一般的であると初めて知りました。
なるほど、水餃子だとたくさん食べられてご飯のようにお腹いっぱいになりました(笑)。
スープもあえて骨付きのものとして、カルシウムと栄養をたくさん取れるようにしました。
○プーアール茶
ヤン先生の中国茶の分類の仕方では、発酵茶と不発酵茶の分類の中で、プーアール茶は、不発酵茶に分類され、
不発酵茶を微生物とともに長時間熟成させた「後発酵茶」です。
この熟成のせいか独特の土っぽい香りがあり、この香りは、一般的に「陳香(ツンシャン)」と呼ばれています。
|

|
|
2.食後のデザート
・タピオカとココナッツジュース
・豆腐花
・パイナップル(ヤン先生の教室で購入した台湾製の缶詰)
・(何故か)スイカ
・凍頂烏龍茶
タピオカは、「出来るだけ中国っぽく」と頑張ってみたデザートです。
タピオカは中華街で買ってきた色つきの大粒のもので、カラフルで食べ応えがあり、ココナッツジュースとよく合いました。
お茶は、私の好きでよく飲む中国茶の一つ、「凍頂烏龍茶」にしました。
さらに、ここで「日頃の練習の成果(?)」をお披露目するべく、工夫茶器で入れました。
|

|
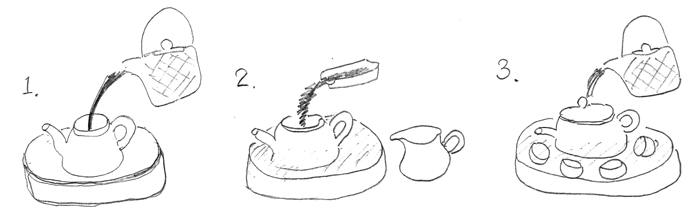
|
|
茶壺に熱湯を入れ、茶壺を温めたらお湯を茶船にあける。<茶壺を温める>
|
|
茶葉を茶壺の底が見えなくなるくらい三分の一ほど入れて、すぐお湯を茶海に入れかえる。<洗茶と茶海を温める>
|
|
もう1度熱湯を茶壺にあふれるほど入れる。茶壺の上からもお湯をかけ、茶船に茶杯を入れて転がしながら温める。<茶杯も温める>
|
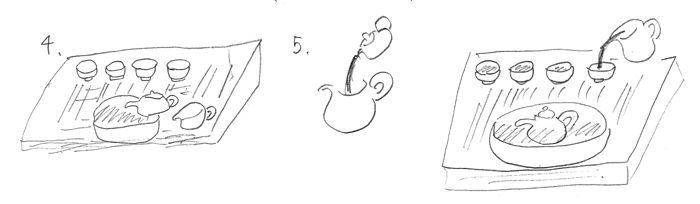
|
|
茶壺を蒸らした後、茶船の縁を使って水気を切って取り出し、茶壺の水気も同じように切る。
|
|
茶壺のお茶を茶海に注ぐ。最後の一滴まで注ぐ。<味を均一にする>
|
|
茶海から茶杯にお茶を注ぎ分けていただきます。日本茶と違って何煎も楽しめ、その度に色・香り・味の違いを楽しめます。<美味しいお茶の出来上がり>
|
|
3.もうひと品
・ドライミックスフルーツ
・四季春茶
○四季春茶:お茶の収穫は春。ところがこのお茶は年中収穫ができるので、年中が春という意味で四季春茶と名付けられました。
このお茶は1990年以降に作られた新種のお茶で、凍頂烏龍茶などの茶種である青心烏龍や青心大冇とは異なる茶樹で、
自然交配で発生したものも改良したといわれています。
風味の特色は、香り高く、爽やかで透明感のある味わいの中に、金萱茶を連想させる甘みが感じられます。
半発酵の烏龍茶ですから、カテキンやビタミンの含有量は凍頂烏龍茶と同じです。
お茶を飲んだ時は知らなかったのですが、四季春茶は、広く烏龍茶に分類される一種でした。
三種類飲んだお茶の中で、彼女は、「四季春」が「香り良く、飲んだ後も良い風味が残る。」と感想を言ってくれました。
「中国茶を始めたのは、あなたの家でお茶を入れてもらったのがきっかけなのよ。」と話したら、とてもびっくりしていました。
彼女は、日本に来て日本人の男性と結婚し、二人のお子様がいらしてもう日本の生活も長いです。
そんな彼女に「日本で、中国茶をこんな風に入れてもらえるなんで思ってもみなかった」と喜んでもらえて、とても嬉しかったです。
お茶会は、美味しいお茶を囲んで、いろんな話をしながら、ゆったりとした時間を過ごしました。
中国茶を味わう醍醐味です。
私のこれからの課題は、もっと中国茶のお茶にまつわる歴史や、効用・効能の知識を増やしていくということと、
実際に発酵茶・不発酵茶・工芸茶・茶外茶といったいろんな種類のお茶を飲み比べ、鼻・目・口といった五感神経を養うことです。
そうしたことを踏まえて、またお茶会を企画し、実際のお茶会では、お茶と集まってくれた人との時間を十二分に楽しめたらなと思っています。
一年前から中国茶を習い始めてから、高校の校外活動以来行っていなかった中華街へ20年以上ぶりにでかけました。
出かける前には、ヤン先生や横浜に住んでいて中華街に詳しい職場の仲間に聞いた店を訪ね、
おいしい中華料理を食べ、「悟空茶荘」で中国茶を一緒に出かけた友人とおしゃべりしながら、
行ったことない中国茶館の雰囲気を想像しながら、ゆったりと時間を堪能しました。
ヤン先生の教室で、茶器セットを購入し、自宅で子供と一緒にドライフルーツを食べながら、
お茶とおしゃべりをする時間も、今は楽しい時間の一つです。
さらに今は、中国茶つながりで、茶芸教室でかじった中国語も、ラジオ講座を聞く楽しみのひとつとして勉強しています。
友人宅訪問でのきっかけが、こんなに自分の生活に潤いがプラスされていくなんて想像もしていませんでした。
何かがきっかけで、誰かと知り合い、何かにめぐり会えていくことに快感を覚えざるを得ない今日この頃です。
日々、人と人との出会いに感謝しつつ、私自身も私の周りにいる人も幸せにたくさんめぐりあえたらなと思っています。
|
|
(江尻 由季 2011年)
|
 |
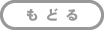 |

