ツバキ科(カメリア・シネンシス)の常緑樹である茶の木の葉から作られている訳ではないが、
お茶のようにして日常飲むものを普通、茶外の茶(茶外茶)という。あるいは非茶の茶(非茶之茶)という。
日常の保健薬として飲むお茶である。
中国医学の集大成(漢代)の結果生まれた二大医学古典の1つ『黄帝内経(こうていだいけい)』
(作者不明)の中に有名な「素問(そもん)」があるが、その内容は”予防医学こと医学の根本
である”というもので、一杯のお茶の意味もここにある。今自分の身体はどのような状態にあるか、
そしてどのような状態にしたいのか。そのことと薬用茶の飲み方は根本で関係する。
|
羅漢果茶 (らかんかちゃ) (産地:広西壮族自治区)
羅漢果はウリ科の蔓性の多年草にできる果実。その果実を採り、熟成させて乾燥
させたものを煎じて飲むお茶。
羅漢果は広西の壮(チワン)族自治区の山岳地帯にしかない果実で、この地帯の瑶(ヤオ)族の医師の羅漢が
薬効を発見したので、この名が付いた。
羅漢果の甘味成分は砂糖の3~4倍あるが、カロリーはほとんどない。そして腸から吸収されず、
排泄される性質を持っており、身体の中に蓄積されない。又、各種ビタミンやミネラルも豊富で、
喉あれ、喉の痛み、咳止め、風邪の解熱、去痰、健胃、整腸、利尿、便秘、高血圧、糖尿病にも
効果あり。又、フリーラジカル(活性酸素等)の撃退にも効果が生じるかもしれないとされている。
|
虫糞茶 (ちゅうふんちゃ) (産地:長江以南の一部の産地)
けしの実のように小さく黒い粒のこのお茶は化香夜蛾(かこうやが)という蛾の幼虫が排泄した
糞である。化香樹というクルミ科の植物の葉、ツバキの葉、もち稲の茎や葉をふるいの上に置いて、
それらの葉に米のとぎ汁をまんべんなく掛ける。葉は発酵し始める。強烈な匂いに誘われて、
化香蛾が飛んできて、ここに卵を産む。卵は約二週間で孵化する。幼虫は発酵したこの葉を食べ、
糞を出す。その糞は化香樹などのエキスのかたまりである。これを集めて、乾燥させ、お茶にする。
小さじ半分ほどの虫糞茶をグラスに入れ、お湯をそそぐだけでよい。肝機能を正常にし、疲労を
回復させる効果や止血効果があるという。
|
寄生茶 (きせいちゃ) (産地:福建省、広東省、雲南省、広西壮族自治区)
寄生植物であるヤドリギ科(桑寄生科)の植物がサザンカや茶の木、ブナの木に寄生する。
その葉を採って、陽に晒し、乾燥した葉を細かく刻んだものを寄生茶、又は桑寄生茶(そうきせいちゃ)
という。
この葉を水から3時間程度煎じる。お湯がお汁粉のような色になるまで煎じる。ほんのり
甘いお茶が出来上がるが、甘味が必要なときは、氷砂糖又は三温糖を少々加える。
寄生茶にゆで玉子を殻をむいて入れ、卵白が茶色に染まるまで一緒に茹でると、桑寄生蛋茶。
ここまでくると、おいしいスープのようなものである。
寄り添う木は桑に限らず、宿った木に従って、名前を付ける。松に寄生すれば松寄生、
柿に絡みつけば柿寄生である。
中国的な思想では、寄生が起こるのは、鳥類が食べた種が糞と一緒に樹木の上に落ちると、
そこに気が生じ、それを樹木が感じて芽を出させ、枝を伸ばすようにさせてゆくからである。
桑寄生茶は毒なし。子供の背骨を強くし、腫瘍を取り除き、肌に生気を与え、髪や歯を硬くする。
筋骨を助け、血脈の流れをよくする。熱を取り、津(しん、水のこと)を生じる。
甜茶 (ティエンチャ) (産地:広西壮族自治区)
瑶族が昔から飲んでいるお茶。
葉を器に入れ、熱湯をそそぐと、葉は器の底に沈み、甘味が生じてくる。甜とは甘いという意味。
甘味は幸せにつながる味として、古来貴ばれてきた。中国では春節に甘いおめでたいお茶を飲む。
甘いお茶の中身は地域によって異なるが、一年中「甜」(うれしい、幸福)であることを願って
飲むところは共通している。
甜茶になる葉はバラ科の落葉する灌木の葉を夏から秋にかけて摘む。ブナ科、ブドウ科、
ユキノシタ科などの葉も甜茶になる。つまり、葉に甘さがあれば、甜茶になるのである。
甜茶の作り方は、摘んだ葉を熱湯にしばらく漬ける。お茶が冷めないうちに取り出し、
干して炒れば、飲用可能な甜茶となる。また、葉を漬けたお湯を捨てないで、そのお湯に
糯米(もちごめ)を漬けて、甘味のある餅を作ったり、粽(ちまき)を作ったりするらしい。
飲むときは、お湯を差すだけでもよいが、煮出すと甘味が増して、さらにおいしい。
七葉胆参茶 (ななようたんじんちゃ) (産地:福建省、広西壮族自治区)
別名:絞股藍茶。
七葉胆は田に生える多年生の草質蔓植物で茎は1~3mも長く細い。横断面は五角形又は
多角形をしている。刈り入れは5~8月。茎と葉を一緒に刈り、5cm 位に切り、緑茶の加工と
同じ方法で加工し、お茶を作る。
中国ではこのお茶に約20%のジャスミン茶を加え、味をより柔和に調えて飲んだりする。
中国では七葉胆(絞股藍)を南方人参と呼んでいる。七葉胆には50種のサポニン(人体の
細胞を生き生きとさせる成分の一つ)が含まれていて、その中の4種が人参のサポニンと同じで、
11種が人参サポニンと酷似している。
七葉胆参茶の薬効は、
・人体の細胞を生き生きさせ、自己治癒能力を高める
・神経衰弱、疲労感、咳などに効果がある
・血液中の中性脂肪とコレストロールを低下させる
・肝炎、糖尿病、胃腸炎、貧血症などに効果がある
といわれている。
副作用はなく、保健飲料として有効に働くお茶である。
|
付記
|
「人参」とは何か?─長い年月の間に生長して、その根は人間そっくりの形になる。
その神秘的なことから”神草”という。人参は五臓を養い、精神を安らかにする。
|
龍茶丸 (産地:福建省武夷山)
武夷山中に自生する薬草30種を端午の節句にお年寄りが早起きして摘み、これを繭状に丸めて
作ったお茶。缶に入れて保管すれば、5年間は保存可能という。高血圧、糖尿病、風邪に
よく効く。
風邪の場合、1個を崩して岩茶と飲む。湯呑みの底に沈んでいる龍茶丸の粉は飲まないようにし、
液体だけを飲み、お湯をたしていくようにする。2~3回飲めばよい。崩さないで丸い状態の
ままで飲む場合は8~9回飲む。高血圧、糖尿病の場合の一般的な飲み方は岩茶約500gと
龍茶丸30個を3ヶ月で消費するように飲む。
雪茶 (産地:雲南省麗江県玉龍山)
雪茶は地茶、太白茶ともいわれる。形は蓮芯に似ている。色が白玉のように白いから雪茶という。
雲南省麗江の海抜4,000m以上の玉龍雪山の万年雪の地に生長する。
雪茶は一般の茶類とは異なり、「本草綱目拾遺」の中では「雪茶は本来非茶類である。草の芽の
一種で、摘み取ったらあぶって飲む」とある。
雪茶の性は温。味は甘く、少々苦味もある。津(水)を生じ、渇を止める。肝臓を鎮静させ、
杯を潤し、胃腸を暖め、血圧を降下させる。糖尿病、急性・慢性咽喉炎にもよい。声に関する
障害にもよい。
明代は皇帝に献上した珍茶である。
飲み方は1~2gでお湯で飲む。あるいは花茶や緑茶に混ぜてお湯で飲む。陶器の皿に乗せ、
微温で炒って、色が黄色になったら湯を差して飲むと、さらに効果がある。
苦丁茶 (クーディンチャ) (産地:福建省、広東省、雲南省)
福建省では苦丁樹(もちの木)の葉で作るという。ほかの省ではオトギリソウ科の植物の葉で
つくるという。
中国の西南地域から江南の人々に飲まれている。
苦丁茶は葉を摘んだら、日干しにするだけでお茶になる。
飲み方は、熱いお湯にほんの少しはを入れればよい。味は茶名とは違い、甘くさわやか。
又、ウーロン茶、緑茶、花茶に混ぜて飲んでもよい。(苦丁茶1:ウーロン茶等9)
薬効は血圧降下、利尿、解毒、のぼせ、解熱、高血糖、耳鳴りなどによい。
|
付記
|
雲南省では、質のよくない大葉種の茶の少し甘味のあるものを苦丁茶ということもある。
|
|
蓮芯茶 (れんしんちゃ) (産地:福建省武夷山)
蓮の実の芯をお茶のようにして飲む。武夷山特産のお茶。蓮子心とも呼ぶ。
苦味の大変強いお茶。ほんの数葉を器に入れ、熱湯で飲む。
苦味は心臓や肝臓に有効に働くと漢方ではいう。体の毒を消し、肺を涼しくさせるお茶である。
杜仲茶 (とちゅうちゃ) (産地:貴州省)
杜仲葉茶ともいう。
貴州省雲霧山中の天然植物杜仲の新鮮な葉で作る。
杜仲は貴州省、陜西省、浙江省に産する多年生喬木で、その皮は漢方の貴重な材料となる。
植えてから皮がとれるまでには10年を要する。その葉で作ったのが杜仲茶である。
作り方は緑茶の方法と紅茶の方法の二種類がある。葉を摘む時期は6月上旬から10月中旬まで。
杜中茶は草の匂いがあるので、30%のジャスミン茶を混ぜるか、中~上質のウーロン茶を混ぜて
飲むとよい。
飲み方は器に少し入れ、熱湯を差せばよい。酒と一緒に飲むと、腰、膝の痛みを治していくと
いう。老化を防ぎ、減肥によく、肝臓、腎臓、高血圧、動脈硬化、頻尿、インポテンスなどの
症状に効果があるといわれる。
柚茶 (ゆずちゃ) (産地:福建省)
中国の柚は大きい。上を丸く切って、中身を出す。空っぽになった柚の中にウーロン茶か、
緑茶を入れ、柚の香りが茶葉に染み込むまで漬け込み、飲むときを待つ。柚の皮も中身のお茶も
カラカラに乾燥したら、柚茶を少しずつ出して器に入れ、熱湯を差して飲む。
薬効は、食あたり、消化不良によい。
八宝蓋碗茶 (はっぽうがいわんちゃ) (産地:甘粛省、青海省、河南省、湖北省)
シルクロードのオアシス甘粛省の酒泉、敦煌から西域に暮らす人々のお茶といってもよい。
暑い夏の日々、人々はこのお茶を飲む。
体熱を外に逃し、肺を清々しくしてくれるからである。
作り方は茶碗に緑茶をほんの一つまみ入れ、次に大きな氷砂糖1個、それから赤棗を2~4個、
桂圓1~2個、白キクラゲ少々を入れ、お湯をたっぷり注ぐ。しばらくすると、底に沈んでいた
緑茶が水面に顔を出し、氷山のようにとがった頭を突き出している氷砂糖の周辺を泳ぐように
浮いてくる。このお茶が八宝蓋碗茶である。氷砂糖がなくなるまで飲む。
八宝蓋碗茶の中身は、土地によってさまざまで、緑茶と氷砂糖は共通だが、クコ、ゴマ、
干しブドウなどを入れるところもある。
|
付記
|
桂圓
|
龍眼を乾燥させた果実で、漢方薬として使われる。味はライチによく似ている。
(薬効)脱毛防止、めまい、産後の肥立ち、貧血、解熱、解毒、止血、鎮痛、不眠、
神経衰弱、リウマチ関節痛など。
|
|
|
白キクラゲ
|
銀耳のこと。
気を増し、身を軽くする。
|
|
|
棗
|
山西省黄河の東、山東省、江南に産するものがあり、菓子によいが、薬として使うには
山西省か山東省の大棗でなければならない。8月に収穫、乾燥する。
性質は甘。毒なし。脾、肺を健康にする。胃の気を平にし、血液の通路(十二径)を助ける。
歯が痛いときは、大人も子供も食べてはならない。
ネギと一緒に食べてはならない。五臓のバランスを崩す。
|
擂茶 (産地:湖南省、福建省)
擂とは、どろどろにするの意。ゴマを擂(す)るの擂。
擂茶は、三国時代(魏、呉、蜀の対立抗争時代)からあるお茶らしいが、ごまのスープといった
方がよいかもしれない。美しい肌を作るお茶として、古くから伝えられている。
|
基本材料
|
上質ウーロン茶、生ゴマ、陳皮、甘草、ピーナッツ(味付けのないもの)
|
分量
(5~6人分)
|
ウーロン茶一つまみ、ゴマ30~40g、ピーナッツはゴマの1/2~1/3量。
以上の材料の他に、薬草を一種類加えて作るケースが多い。
|
|
作り方
|
1)すり鉢でウーロン茶をよくする。
2)ゴマを入れ、茶葉と一緒によくする。その後、水を少々差し、再びする。
3)甘草とピーナッツを入れる。
加えたい薬草があれば、この段階で入れてよくする。
4)どろどろに柔らかくなったら、すり鉢に熱湯を八分目まで入れる。
表面にアクが浮き上がっていたら、きれいにとる。これを器についで飲む。
|
|
注意
|
生ゴマを使うために、日もちはしない。その日のうちに飲んでしまう。
|
|
付記
|
甘草
|
筋肉の急激な緊張による痛みを解く。咳を鎮め、痰を取る。胃痙攣、胃痛などによい。
大変甘いので、最近は砂糖の代用品として使われている。
|
|
|
陳皮
|
カンキツ類の皮を干したもの。食欲不振、嘔吐によく効く。
|
|
|
(礒永 智子 2001年)
|
 |
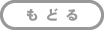 |

