|
近年、茶の発祥の地である中国(主に台湾)にて、培ってきた茶の伝統、文化を改めて後世に
継げようという活動が盛んです。泡茶とは「茶を入れる」という意味があります。功夫茶器を使い、
伝統式作法に基づき、茶を入れます。
功夫(コンフー)とは日本語の「工夫する」とは少々意味が異なり、
「技がある」という意味もあります。
茶器の名称は、茶壷(日本での急須)、茶海(ピッチャーの役割)、茶船(湯を注いだ時の受け皿)、
茶杯が基本です。茶杯は必ず偶数で揃えます。
これは中国人が偶数を縁起が良いととらえているからです。
中国では、地方によっては茶杯の数を6個は冠、10個は婚礼、12個は祭り事のときと使い分けて
いる様です。
茶会を催した際、集まった人数が3人、5人と奇数であっても、茶杯は4個、6個と用意し、
茶を注ぎます。
|
|
本題の入れ方ですが、伝統式について説明します。茶船の中に茶壷を置き、茶杯を並べ、茶海を
置きます。
まず、軽く温めるためもあり、茶壷に湯を注ぎます。
その湯を茶船に捨てます。
茶船に注ぐ事で後に茶器全体を温める作用をさせます。
茶荷から茶さじにて茶葉を茶壷に入れます。
茶葉の目安としては茶壷の底が隠れる位が一般的です。
湯を注ぎますが、この茶湯を一度茶海に入れます。
いわゆる洗茶という作業です。
洗茶の由来は茶についているホコリ等を取り除く衛生面でのためですが、
近年はこういった心配はなくなっています。
伝統式では改めて洗茶を行う事で茶葉の開きを良くし、
また茶海に香り付けをする意味が込められています。
再度、茶壷に湯を注ぎ茶杯もまた茶船に入れます。
そして、茶壷のフタの取手に向って湯を注ぎます。
目安としては、茶船の8分目位です。
茶葉の蒸らし時間は約3分。
この間に茶杯を指で回し、全体を温めます。
その後に、茶杯を一つ一つ底を切る様に取り出し、茶海の茶を捨てます。
茶壷を取り出す際、茶船の縁の上を反時計回りで擦るように回します。
これは、「来来来、喝茶」というもてなしの重要な意味があります。
時計回りは「お別れ」を表しています。茶海に注ぎ、茶湯を均一にさせます。
最後に茶杯へ注ぎ、客人にもてなします。茶海に注ぐまでを3分間としています。
|
|
茶を入れる際、とても重要な事は、「茶器を必ず温める」ことです。
これは、中国茶で重視される香りを逃さないためです。
最後に、伝統式茶芸の持つもう一つの文化的な面は、お茶を入れることで客人との会話(親睦)を
深めるコミュニケーションとしての役割があることです。
人が集まり、お茶でもてなす。
お茶を飲む時間を大切にする数千年来の精神文化を引き継いでいくために、
伝統式茶芸の更なる発展が必要であると思っております。
|
|
(金子 2001年)
|
 |
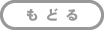 |

