|
中国の喫茶文化の歴史をたどっていくと唐から明にかけての時代が最も変化が大きく、
その節目ともいえるのが1319年固形茶製造廃止宣言です。庶民から起こった明の太祖
朱元璋が贅沢に作る固形茶を単に排撃しただけでなく、宮廷・文人の上流階級の趣味で
あった茶文化を社会全体の生活文化へ変えていった時代でもあります。固形茶から葉茶へ
主流の変化は社会の各階層に及び、風俗・人生の儀礼(婚礼)などと結びついて庶民生活と
深くかかわっていきます。実際にはこの変革以前より、もともと安い葉茶に調味料・香辛料
を入れた雑茶が一般庶民の間で普及しており、太祖のおふれはそれ程混乱を招くものでは
ありませんでした。茶の製法は無論飲用法の変化へとつながり、上流の文人たちの茶書の
出版・宣伝により深く大衆生活に浸透していく習慣となります。それはそれまでの茶を
飲むという一種の物質的消費だけでなく精神的な生活芸術として喫茶文化を昇華させ、
同時に雑茶を排斥運動から衰退へと向かわせていくのです。
|
|
茶葉を出す茶器として茶壷が中心に登場するのもこの頃、中でも供春や時大彬の
宜興紫砂泥壷に関心が集まります。そして、より一層茶の真味真口を楽しみたいという
願望が比較的小さな急須へと移行し、貢献したのが恵孟臣・陳鳴遠などの名陶工でした。
許次紓著「茶疏」にも「茶注(茶壷)は小さいのが良い。大きすぎるのはよくない。
小さいと香気がこもる。 独りで飲むなら、さらに小さければ小さい程よい」と記されて
います。
|
|
工夫という飲み方は広東省東部や福建省に流行したもので、発祥源は汕頭地区と
福建南部一帯といいます。宋の時代から始められた「小杯茶」(小さな杯で茶を飲む)が発展、
変化したものが工夫茶であり、手間ひまをかけて細心の注意を払い丹念な手順で鉄観音、
武夷岩茶、水仙茶などの清茶(ストレートティー)をおいしく飲む為に文字どおり工夫怠り
なく考えられた入れ方です。潮州・汕頭地区では喝茶という代わりに品茶(茶の香味を
テストする)という程お茶は好まれています。、茶道具も「潮汕烘炉」(素焼きコンロ)、
「王書碨」(白泥横手湯沸かし瓶)、孟臣罐(恵孟臣作の急須など宜興壷)、
「若琛瓯」(一口大の盃、内側に白い釉のかかったものが良い)とあり、これらを「四宝」と
称して、喫茶に凝る人々はこれを揃えることを楽しみにしているといいます。
日本の「茶道」のような飲み方といえば「茶規」に基づくものがあり、「洗茶」、
「関公巡城」(茶の色を等しくする)、「高衝低斟」(高い所から湯を注ぎ、茶は杯に接して
入れる)、「草韋信点兵」(残り僅少のとき、各杯に一滴ずつ入れるようにする)などの
手順があり、茶湯の色が濃いのや薄いのがあるのは「破茶胆」、「犯茶規」といって嫌うのだ
そうです。更に茶かすをごしごしと洗ってはならず、潮州では熱心のあまり間違ったことを
する人を「洗茶渣」(茶かすを洗うの意味)ともいい、茶かす落しに熱中して急須をこわすのは
おろかなこととされています。
|
|
台湾でも現在工夫茶芸がたいへん盛んです。連雅堂著作の「台湾通史」では1800年前後
柯朝という人が福建省武夷より茶の種を持ち帰り、台北周辺に植えたという記録があります。
台湾は福建省地形・気候の類似から茶樹の発育が可能となり、お茶の発展へとつながって
きました。しかし一方、中国では清朝末期の1890年代から戦争と革命が続いて製茶や工芸
及び喫茶文化とも没落に向かいます。中国大陸の茶文化が衰退していった時、海を隔てた
台湾の茶は歴史的条件の相異から製茶技術・喫茶文化(明から清への発展)を受けついで
新展開します。
イギリス商人によってフォルモサウーロン(東方美人)が高い評価を受けて国際的に名が
知られ、輸出向けに大量に生産が始まります。日本統治時代には機械化・近代化した生産
販売の基礎もできます。第二次世界大戦後も輸出が主でしたが、1970年代中頃、世界的な
石油危機の始まりで茶の輸出価格は暴落します。痛手を受けた農民が国内市場へ転換する
こととなったのです。この1970~80年代は台湾の茶文化にそれまであった富裕階級と
庶民との間の境界線が曖昧になり、国民経済状況の変化によって誰もが良質のお茶を買える
ようになった時代です。そして自然に茶器や環境もそれに合わせようと選ぶようになり、
全体的な環境を重んじる茶の文化が大衆に普及していきました。
|
|
現代、特に台湾では多くの
種類の茶道具が出ており、どうしたら香り高いお茶をおいしく飲めるか、近年各地に開かれた
茶芸館で多くの人々が工夫茶の製法を学ぶ茶芸ブームが加速しています。こうした中、茶芸
精神・喫茶思想の追求は更に中華茶芸を確立する方向へと向かわせているようです。又、音楽
茶会や書画を描いてその場で批評したりする茶会も行われています。かつて宋や明の時代の
文人達はお茶を飲みながら世について文化について論じたといいますが、現代もお茶を通して
なにか哲学的なことでも見出そうとしているかのようです。そうなると自らも常に向上し、
器を大きくしていかないと、お茶本来の真味真口は知ることができないということになるので
しょうか。
|
|
お茶を飲むことは今の生活の一部分であり、その時々自らがどのようなお茶を
飲みたいのかも、もちろんお茶を楽しむことだと思います。
|
|
(木村 美奈子 2001年)
|
 |
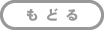 |

