茶の分類方法は色々あるが、発酵の度合いで発酵茶と不発酵茶に大きく分けることができる。
茶の発酵とは、茶葉に含まれている酸化酵素の働きで茶の中の主成分であるタンニンを
酸化させることをいう。
半発酵茶という分類を作ることもできるが、それぞれの境界は明確ではない。
発酵茶には烏龍種・包種種・紅茶種などがあるが、
有名な産地の名前やブレンドしたフルーツや花の名前が商品名として付けられたため
分類を詳細化しようとしたらとても複雑なものになってしまう。
本来、中国茶のほとんどは発酵茶である。
一方、不発酵茶は緑茶種で、有名なものに龍井茶・珍しいものに珠茶・碧螺春・瓜片などがある。
緑茶種は酸化酵素の活性を止めるため、茶葉を摘んだ後すぐに熱を加える。
日本茶の場合は蒸す方法を取ることが多いが、中国緑茶は釜炒りする。
この処理を殺青というが、これによって茶の緑色、ビタミンCなどが多く残る。
なお、一部の白茶、黄茶類は古い資料では緑茶に含まれていることもある。
それは、茶摘み後にすぐに一旦発酵を止めるが、後の工程で発酵させることがあるからである。
このような茶は後発酵茶とも呼ばれる。
発酵茶である紅茶は葉を摘んだ後、萎凋(withering,、しおらせること)、
揉捻(rolling、もんで茶汁を出やすくすること)、ふるいわけ(sifting)、発酵(fermentation)、
乾燥(firing)という過程を経て、製品の前段階の荒茶が出来上がる。
発酵茶の中でも烏龍種、包種種については最も複雑な工程を経て出来上がる。
例えば、烏龍茶の製造工程は以下の通り。
茶摘み→萎凋(日光萎凋、室内萎凋)→做青→炒青→揉捻→烘焙
不発酵茶である緑茶種はタンニン(渋味)を押さえて、アミノ酸(うまみ)を
ひき出させるために、比較的低い温度の湯で淹れると良い。
(龍井茶は熱湯で淹れた方がよいと楊先生の説。ただし、日本風に味わいたければ、
日本茶の淹れ方に準じてよいとのこと。)
発酵茶は発酵の度合いにもよるが、熱湯で淹れるのがよい。
発酵茶の美味しさは主にタンニンにあり、タンニンは80℃以上の熱湯で段階的に
とけ出すことと、お茶独特の良い香りの源である芳香油が熱湯を注ぐことで
効果的に揮発するからである。
|
|
(中原 祐美 1998年)
|
 |
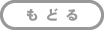 |
|

