|
中国茶の中で最も古い歴史を持ち、現在の中国本土で飲まれているお茶の80%くらいを占有している。
江南地方と長江流域に有名な産地が多いが、
福建省、雲南省など烏龍茶、普洱茶の有名なところでも生産はされている。
宋代までは献上茶は、固形茶であったものが、
明代、洪武帝の時に労力を必要としすぎるという理由から、固形茶が禁止され、以降、緑茶は
散茶の形をとるものが発達してきた。一般に緑茶は不発酵で香りは豆や草にたとえられ、
水色はグリーン系とされている。
ただし、有名な龍井茶は、殺青の前に4時間ぐらい日光の下に置かれるために萎凋とまでは
いかなくても、かすかな発酵はされていると思う。
そのため、茶葉は茶色みがかり、香りに甘みがかもしだされるのであろう。
製法は、茶葉を摘んだ後、青殺を行い、発酵を止め、揉捻した後、乾燥させる。
青殺には蒸し煮と釜炒りがあり、前者は日本で普及され、後者は中国での主流である。
なお、日本でも嬉野茶は釜炒りで、中国でも恩施玉露は蒸し茶というように国での線引きはできない。
|
|
中国緑茶という課題なので、とりあえず主流の釜炒り製法について以下は述べ、蒸し煮は省略する。
まず、釜には①水平釜と②傾斜釜がある。①は上級緑茶類に使用され、②は平水珠茶、屯渓珍眉、
秀眉などで使用される。
釜の温度は低いもので碧螺春の70~80度、高い方では黄山毛峰の150度があり、さらに200~300度の
高温で行われるものもある。
火入れは主に3パターンあり、炒る→揉捻→炒るの後、乾燥されるものが炒青。
炒ってから籠に入れ炙り乾燥させるのが烘青で、この方法だと揉捻が行われないので白毫が残る。
2つを合わせたものが半烘青(または半烘炒緑茶)といわれ、望府銀毫や午子仙毫に使われる。
炒青には茶の葉の形が長条形の長炒青(主に眉茶と称されるもの)、珠形の円炒青(主に珠茶と
いわれるもの)、やわらかい芽を摘んで炒青する細嫩炒青がある。
細嫩炒青は高級茶になるものが多く、龍井、碧螺春、雲霧茶もこの方法である。
烘青は花茶に使用されるが、細嫩炒青は毛峰系のお茶となり、代表的なのが黄山毛峰、敬亭緑雪である。
以上は散茶に使われる炒青であるが、他に緊圧茶となる曬青がある。
これは炒った後すぐに日光で乾燥するものである。
揉捻は行う方が茶葉内の成分がまんべんなく行きわたり、湯で出し易くなるものの、見た目の美しさでは
白毫の残る毛峰や迎春茶の方が美しい。
|
|
個人的感想だが、味で選べば龍井のように茶色がかっても日光にさらし、揉捻した方だが、
見た目をとると味の方が少し劣っていると思う。
緑茶を入れる温度は低く言われているのでは60度くらい、さらに低いと水出しの方が旨味成分が出るという説まで
あるが、香りには欠けるものがあるように思う。
私は中国緑茶は香りも楽しめる90度くらいが一番美味しいと感じている。
|
|
(山本 淳子 2002年)
|
 |
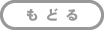 |

