羅漢果と言えば、筆者にはさまざまな思いが交錯するフルーツのひとつです。
80年代のことですが、当時筆者は勤めていた会社で、
多くのアナウンサーが美声を保つために求めている「神果」(神仙果)を輸入できないかとの相談を受け、
それに応えて「神果」の輸入に踏み切ったのを思い出します。
その後、栄養分を調べたところ多くの薬効があることが分かり、
多くの健康商品が作られたことは皆様もご存知だと思います。
当時の中国は通信事情が悪く、中国語しか通じないので、筆者が実務を担当しました。
また、貿易に関する考え方もやり方も違い、多くの方々の努力により、無事に「神果」を日本に輸入し、
それを商品化して定着させることができたのを、今でも誇りに思っています。
羅漢果の学名はMomordica grosvenori、ウリ科ツルレイシ属(ニガウリ属)の多年性つる性の植物です。
中国広西チワン族自治区を原産地とし、桂林市の永福県、臨桂県と柳州市融安県などで生産されています。
総生産量の80%が永福県産で、永福県の主要輸出品になっています。
中国広西チワン族自治区はベトナムと隣接し、チワン(壮)族(旧字僮族)を初め、多くの少数民族が住んでいます。
人気の観光都市桂林は元々百越族が住み、秦の始皇帝が南越を征服して置いた桂林郡の地と伝えられ、
景色が美しいのが有名です。
山水甲天下(景色が天下一)と称され、1940年の抗日戦争時期、中国各地から多くの文化人が集まってきたため、
「文化之城」とも呼ばれています。
以前は広西省と言われていましたが、1958年に広西チワン族自治区に改称されました。
龍勝梯田(棚田)は有名な観光地であり、黄洛紅瑶寨では多くのヤオ(瑶)族の女性が髪を長く伸ばすことから、
ギネス・ブックに世界一の長髪村として認定されています。
また、ヤオ族は「打油茶」をよく食べます。
この一帯の有名な小吃(小腹が空いたときの手軽な食事)にもなっています。
それぞれの家庭に伝わる作り方がありますが、一般的な作り方は生の茶葉を炒って、
水、ピーナッツ(揚げピーナッツも使われます)、米花(お米かモチゴメを揚げたもの)、塩、生姜を加えて、
炒め煮します。
食べながら飲むデザートです。
このためか、この一帯ではよく庭にお茶の木を植えています。
永福県は桂林市の西南に位置し、「福寿之郷」(長寿の里)として有名です。
また、青磁で有名な永福窯があるのでも知られています。
永福窯は宋の時代より青瓷を焼き始めました。
製品は主に碗や皿の生活用品が多く、一部壷や急須も焼いたようですが、
青磁の名窯で、唐の時代よりの陝西省銅川市の耀州窯に強く影響を受けたとされています。
作風は刻花(事前に文様を彫り付けたもの)や印花(型に模様を作り生地に押す)の技法が多く、
菊の紋を多く使っているのも特徴です。
羅漢果は約300年前から薬膳的に食されてきたとされていますが、
広西省桂林では200年ほど前にヤオ族出身の羅漢という名の医者が薬効に気がつき、
人工栽培を始め、治療に使ったことが名前の由来とされています。
羅漢果は雄と雌の株に分かれ、夏季に開花し、秋に実を結びます。
果実が羅漢果と呼ばれています。
熟後の果実は、5日から1週間放置し、45から65度にて焙煎します。
そのまま食すこともできますが、果肉や皮すべてに甘みがありますので、果実全部を食すことができます。
ちぎって水で煎じて、お茶として飲むのが一般的です。
また、中国人の食習慣ではあまり冷たくしたお茶は飲まないのですが、
夏などでは羅漢果茶を「涼茶」冷まして飲むことがよくあります。
もちろん、糖が気になる方は料理などの砂糖代わりとして使うことができます。
また、ツバキ科のお茶とともに煎じて飲むこともできますので、楽しみ方が豊富なのも特徴です。
楊品瑜 2008.09.10 (転載不可)
|

羅漢果
|
|
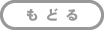 |
|

