霍山県は安徽省西南部の六安市に属し、県西部の一部は湖北省の英山県と接しています。
霍山県の地名は県南の霍山にちなんで名付けられたのです。
その歴史は古く、春秋時代では楚国に属し、“潛”と呼ばれ、
楚漢相爭(秦末の楚王・項羽と漢の高祖・劉邦の天下争い)の時に衡山国と改められました。
南北朝時代に梁朝がここに霍州を置き、隋の開皇初頭に始めて霍山県が設けられました。
唐以後は開化県、武昌県、盛唐県と称されることもありましたが、宋代は県を廃し鎮を設け、六安州に属しました。
古い港町であり、明弘治年間に再び霍山県に昇格し、今日に至っています。
霍山黄芽は、唐代の李肇『國史補』に紹介されています。
その記述によると霍山黄芽は、十四品目の貢茶(朝廷に献上する茶)の一つに列せられています。
明代王象亞の『群芳譜』にも寿州霍山黄芽を佳品と賞賛しています。
寿州は、現在の安徽省六安市にあたります。知名の寿州窯は唐代七大瓷窯の一つでありましたが、
陸羽は『茶經』に「寿州瓷色紫」(寿州の瓷は紫色)と言い、「寿州窯列為第五位」(寿州窯を第五位)に列しています。
清朝、曹雪芹著『紅楼夢』にも寿州窯が取り上げられています。
霍山県は、亜熱帯の湿潤季風気候と半湿潤季風気候の過渡地帯に位置しています。
自然資源が豊富で、鉱物は約23種、漢方薬材は1460種以上あり、水も豊富でダムが作られています。
ゆえに“金山藥嶺名茶地,竹海桑園水電郷”と称されています。
豊かな自然と共に、希少動植物も多いところです。
霍山黄芽は、製法上黄茶に分類されています。
黄茶は一般に黄芽茶、黄小茶、黄大茶の三大分類によって作られます。
黄芽茶とは新芽または一心一葉だけを使って製茶、
黄小茶は柔らかく若い新茶、黄大茶は少し成長した茶葉で製茶したものです。
製茶工程は、一般に茶葉萎凋(この工程は職人によって行わないこともあります)後、殺青を行い、
揉捻、乾燥、そして悶黄(もんこう)を行います。
悶黄とは渥堆ともいいます。
高湿度高温の環境下で牛皮紙(クラフト紙)に包み、茶葉が成熟させていく工程です。
ただし、取材した感じでは悶黄の方法に関して、工程上いつどこで、どれぐらいの時間で行われるのかは、
職人によってまちまちでした。
ただ、乾燥を行う前にやるのが一般的なのかも知れませんが、
悶黄は黄茶製造においては、もっとも重要な工程であるこには変わらないです。
霍山黄芽は暫く生産が途切れていましたが、1971年に生産が再開され、1985年に香港に輸出され、
その後東南アジアの華僑向けにも輸出し、銘茶としての地位を復活させた経緯を持つお茶です。
飲んだ感じでは、少々個性のあるお茶ではありますが、ほのかな甘みがあり、
上手に淹れられたら、きっと病み付きになる一品ですね!
楊品瑜 2011.12.05 (転載不可)
|

|
|
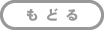 |
|

