桐木紅茶は福建省武夷山市(旧称崇安県)星村郷桐木関一帯で生産された紅茶です。
武夷山北端海拔約1000~1500メートルの地帯で栽培されています。
冬暖かく夏涼しく、通年雲や霧に覆われた気候です。
桐木紅茶は「桐木関小種」、「星村小種」や「正山小種」と呼ばれ、
武夷山以外で作られたものや似せたものは「外山小種」「人工小種」として区別されています。
桐木紅茶(正山小種)の英名は「LAPSANG SOUCHONG 」(ラプサンスーチョン)と呼ばれています。
LAPSANGの由来は諸説ありますが、明末清初の時代に福建省の行政中心都市であった福州市の輸出業者が、
燻製に使った松の木の名前をブランド名として付けたと言われています。
福建省の省都である福州市は、閩江口の左岸に位置し、古くから東南の海港として知られ、
明清時代には最も繁栄を遂げました。
造船業が盛んで、明初鄭和が大航海で使用した寶船(またの名は寶舟、寶舡)は福州で製造したものとされています。
また、明清時代、琉球王国との交易の指定港にもなっていました。
清末では造船工場として福州船政局(馬尾船政局または福州船廠ともいう)が設けられ、
江南製造局とならび、清末の代表的な官営軍事工場となっていました。
なお、福州市は茶や木材を中心とする地方物産の一大集散地であり、
アヘン戦争後、清朝と英国の間に結ばれた南京条約(1842年)により、5通商港の一つとして開港されたのです。
SOUCHONG は小さい茶葉の品種、「小種」に由来します。
そして、「LAPSANG SOUCHONG」は、当時は紅茶という概念がなかったのですが、
福建茶の代表とされたBOHEA茶(武夷の福建語発音にちなむ)と区別するために、
異なった品種の用語として使われたそうです。
お茶の誕生秘話として、明末の戦乱において、
ある日突然この一帯に軍隊が駐在したために茶葉の製茶ができなくなった。
そして軍隊の撤退後、製茶の業者が慌てて完全に発酵してしまった茶葉にあるだけの樹木、
主に松の木(松柏)を使って焙火(焙じた)したため、偶然にも薫製茶ができたと言われています。
また、兵士が駐在中に茶工場で寝起きしたため、下敷きになった茶葉をしかたなく、
あるだけの樹木、やはり松の木で焙じ、偶然の産物で生まれたお茶とも言い伝えられています。
オランダ人が初めて輸出した中国茶または紅茶がこの茶だったという説もありますが、定かではないようです。
ただ、ヨーロッパに輸出され、オリエンタルな香りがするお茶として人気だったようです。
また、当時の輸送事情から考えても日持ちや船での輸送に耐えられるようにと、
不発酵茶より半発酵茶、そして完全発酵の紅茶の方が輸出の主力品になったのであります。
日本ではラプサンスーチョン茶は漢方薬っぽく、クレオソートの香りがするお茶として好みが分かれるお茶ですが、
中国では龍眼乾(ドライ龍眼)または桂圓の香りに似ていて好まれています。
また、日本ではミルクティーとして飲まれることが多いようですが、
高級なものはストレートで飲んでも茶の甘みが美味しく頂けます。
香りは、筆者や主宰する教室の受講者は慣れたせいか、クレオソートとの区別がはっきりとわかるようになりました。
楊品瑜 2010.03.20 (転載不可)
|

桐木紅茶
|
|

|
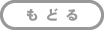 |
|

