佛手茶の名産地は福建省泉州市永春県蘇坑、玉斗、桂洋等海拔600~900mの一帯です。
永春県は歴史が古く西周から春秋戦国時代に閩越(文献によると今の福建省の沿海地方は古代越族の居住地、後に漢族が南下し、
越族は次第に南へ移り、大多数はベトナムに入った)五代後唐時代では長興四年(933)に桃源県となり、
後晋天福三年(938)に永春県となりました。
「桃源県」の名の由来は、用水が桃渓を源にしていることから「桃源」とも呼ばれていたのですが、
湖南省の桃源県と地名が重複すると言うことで、草木が青々と茂っている環境に四季は春の如くということで、
「永春県」と改名したのだそうです。現在でもその名残なのか、湖洋鎮に桃源村があります。
永春県は佛手茶、佛手柑の名産地です。
佛手茶や佛手柑の名の由来は、仏(佛)様の手に似ていることから佛手と名がつきました。
佛手茶又の名は香櫞種、雪梨です。
名の由来は諸説ありますが、
摘まれた茶葉が数枚繋がっている様子が同じく名産品の佛手柑のように見えることからその名がついた説があります。
名貴勝金(名高く金に勝る)として「金佛手」とも呼ばれているそうです。
一方で、清康熙1704年に永春獅峰岩が作られた時に、仏に捧げるために一帯に植えたところ、
一望にりっぱなお茶が育ったので、「佛手茶」と呼ばれるようになった言い伝えもあります。
また、永春佛手は、北宋の時代に安溪県騎虎岩寺の和尚さんがお茶の木を佛手柑の木に接木し、丹念に育て、
後に弟子がその栽培法を伝授した説までがあります。
佛手茶の製法は、烏龍茶と同じく半発酵茶です。
午後に茶摘みし、夜に製茶をしています。
茶摘みは四~五葉,新芽は摘まず、その下二、三葉を中心に茶摘みをします。
製茶過程は、一般烏龍茶と同じです。
入手した佛手茶は茶葉が厚く、茶湯も濃厚でやや渋みがありました。
しっかりした烏龍茶味を味わいたい方にはお勧めです。
楊品瑜 2015.01.08 (転載不可)
|

永春佛手茶
|
|

|
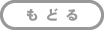 |
|

