南京市は江蘇省の省都で、中国の悠久な歴史の中でも多くの時代で首都が置かれ、
北京、西安、洛陽と並び中国四大古都とされています。また、長江(揚子江)の下流に位置し、
229年に東呉の孫権が遷都して以来,十の王朝が都としたことで、“十朝都会”とも呼ばれています。
近代に於いては南京国民政府の首都であったことでも知られています。
別名に金陵、清朝では江寧と呼ばれていたため、略称に「寧」が使われています。
雨花茶の歴史は四世紀頃の東晋時代に遡り、南京市民は飲早茶(モーニングティー)を飲む習慣があったと、
陸羽の《茶経》の中の“広陵耆老伝”に記述があります。
内容は、「晋元帝の時代に、ある老婦人は毎日早くから一壷(ワンポット)の茶を持ち売っていた。
百姓は競って彼女の雨花茶の茶湯を買った。
不思議なことに、この老婦人は朝早くから夜遅くまで茶を売り、その売上を全部貧困な人に配った。
貧困な人たちからは大変感謝されたが、このことを知った役人は老婦人を捕らえ牢屋に入れた。
なぜ捕らえたのかははっきりないが、翌日朝老婦人は牢屋から消えていた」という話です。
また、唐代の皇甫冉の詩「送陸鴻漸棲霞寺採茶」に当時の南京での茶摘みの苦労話があります。
棲霞寺は中国仏教三論宗の発祥地で南京近郊に位置し、陸羽(字は鴻漸)が身を寄せたことがある寺です。
一説では、乾元2年(759年)に皇甫曾、皇甫冉兄弟と知り合い、詩はそのときに陸羽に送られたものです。
当時の茶樹は棲霞寺の近くの崖に生息しており、そんなところに茶を摘みにいく陸羽を称えて、
「日が暮れようとしてもまだ茶摘みが終わらず、あげくに野宿して茶を作る、
その精神はすばらしい、しかしいつになったら茶湯が飲めるだろうか」というような意味になっています。
現在の雨花茶は、1950年代末から緑茶栽培が再開され、
1960年では中国の十大名茶のひとつとして評されるほどに再評価されています。
栽培地は主にブランド名の由来となった雨花台です。
雨花台は中国の詩にもよく登場する美しい地名ですが、歴史においては、多くの人たちが血を流した場所として知られ、
現在は平和の祈りから「南京雨花台烈士陵園」が作られ、樹木の栽培を増やし、観光地にもなっています。
この樹木の栽培とともに、茶園も拡がったと言われています。
筆者の雨花茶との出会いは、十数年ほど前の教室で訪れた横浜中華街の茶芸館です。
南京の茶が珍しかったのがきっかけで注文したのですが、今でも最初に飲んだ味をはっきりと覚えています。
とても苦いのですが、茶の味は薄い感じでした。
同行した人からはどうしてこんな茶を選ぶのか不思議がられました。
それでも、その後も行くたびに同じ店にお願いして、南京雨花茶を飲んでいます。
なぜなら、毎年茶園に行くことはできないですが、毎年の茶樹の成長を味わっているからです。
特に新しく植えた茶樹は早くても5~10年してから、
茶農によっては30年育った茶樹からよい茶が採れると言われていますので、
筆者流の楽しみ方にも同感いただけると嬉しいです。
ここ数年の雨花茶は、茶樹が育ってきました。
また、茶農の技術や機械が向上し、とてもまろやかで飲みやすい中国緑茶の味になっています。
茶(製茶したもの)を数年寝かして楽しむ中国茶(主に発酵茶)好きも多くいますが、
茶樹の成長と共に茶を楽しめることは、自分も共に成長している気持ちとなり、心を豊かにしてくれます。
南京市では雨花茶節(祭り)を定期的に開催し、南京の特産品として成長を遂げています。
更なる発展が楽しみです。
楊品瑜 2006.04.10 (転載不可)
|

南京雨花茶
手書きのラベルが貼ってあるだけです。
|
|

|
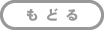 |
|

