安吉は浙江省の西北部に位置し、長江の三角州の経済区として発展してきました。
約1800年前の東漢の時代に県となり、
漢霊帝により詩経の“安且吉兮”に由来して安吉と名付けられたとされています。
現在の行政では安吉県は湖州市の管轄になっています。
湖州市は古くから「絲綢之府﹑魚米之郷﹑文化之邦(シルクの都市、魚米の里、文化の邦)」と称されています。
“文房四宝の故里”と言われるほどに芸術文化都市です。
茶聖 陸羽は湖州に隠居したときに「茶経」書いたとされています。
また、安吉は竹の名産地としてもよく知られており、“世界一流の竹種園”と称されています。
一般に“中国竹郷”と呼ばれ、300種類あるそうです。
安吉白茶は浙江省安吉県山河郷大渓村産の銘茶です。
産地名から「大渓白茶」とも呼ばれています。
宋の皇帝徽宗(趙佶)の著書「大観茶論」では“禦賜白茶遂為第一銘”一番良い茶と絶賛していました。
後に絶滅に近い状態になりかけた安吉白茶ですが、安吉県の大溪山の海拔800mあたりで、
1982年に偶然樹齢百年を超えた一株の古樹が発見されました。
その後、十数年かけて再生し、今日に至っています。
現在は主に長興、德清、浙江省北部の茶区江蘇、安徽などの省でも栽培されています。
1998年には浙江省農作物品種審定委員会が認省級品種として認定しています。
茶樹はやや小柄とされ、茶葉は細長く、茶湯はきれいな水色で、
味がほのかに甘く本当に美味しい中国緑茶です。
春に採取した茶葉は「白化現象」という葉が白くなるのがこの茶名の由来です。
実は、玉露の生産量日本一の八女にも、生産量が60~80kgという貴重な八女白茶があります。
2002年に教室で視察に行きました。
そのときの八女白茶生産者の話によると、
「八女に限らず、もともと茶樹の栽培で葉が白く出てくることがあるが、育ちが悪いし、
色が違うことで商品価値も低いとして、抜いて捨てていた。
しかし、あるとき飲んでみたら大変美味しく、一般の緑茶よりグルタミン酸が豊富で、
甘味が強くとても飲みやすかった」のだそうです。
さらに中国に白い高級緑茶があると聞きつけ、
「これもなんとか商品に出来ないかと栽培したのが八女白茶のきっかけ」だったそうです。
八女白茶視察がきっかけになって、
婆茶室主宰の陸千波さんの知人がお土産として安吉白茶を持って来てくれました。
交通の不便さと安吉白茶の生産量がまだ安定していないために、
コネがないと入手困難な茶だったので感激して、教室参加者で美味しく頂きました。
中国人はよく人との出会いは「有縁」(縁があるから)と例えます。
縁があって出会った陸千波さんのおかげで、美味しい安吉白茶が飲めたことに感謝します。
生産者の方のアドバイスもありまして、
個人的には八女白茶と安吉白茶は高温で入れて飲んでいます。
茶の甘味がよく出て、さわやかな味わいが楽しめます。
楊品瑜 2007.01.15 (転載不可)
|
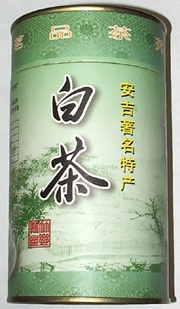
安吉白茶
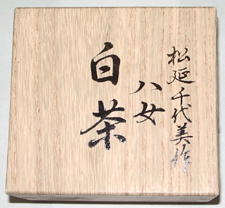
八女白茶
|
|

|
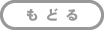 |
|

