杉林溪茶区と凍頂鳥龍茶区はともに南投県に属し、
隣の茶園と例えてもよいくらいのご近所茶区です。
杉林溪は南投県の西南端の竹山鎮に属します。
竹山は古くは 「二重埔」 や 「水沙連」 と呼ばれていましたが、
1664年に鄭経のとき、
部下であった林圮の部隊が濁水渓に沿って沙連蕃地を竹で囲んで開墾の拠点としたことにより、
「林圮埔」または「竹囲庄」と呼ばれました。
今でも竹製品の名産地で、70~80種類の竹が自生したり、栽培されたりしています。
郷土料理には筍料理や竹筒飯など竹を活用したものが多くあります。
隣接した凍頂があまりにも有名なために、竹山では茶がほとんど生産されていませんでした。
50年ほど前、鏡照山や坪頂埔の標高の低いとろで栽培が始められ、照鏡山茶と呼ばれました。
その後、徐々に海抜が高いところでも生産されるようになったために、
近年は慣習として照鏡山茶を杉林渓茶と呼ぶようになったそうです。
ただし、照鏡山の名前は照鏡山黒茶や照鏡山佛手茶という個性的な茶には残されていますし、
竹山烏龍茶や竹山金萱茶など竹山の名前が付いた茶もあります。
杉林渓茶区もやはり、開発されて20年程度の新興茶園のひとつで、
主に青心烏龍で高山茶が生産されています。
他に、金萱も栽培されており、杉林渓金萱も作られています。
気候は茶栽培に適し、美味しい茶が採れますが、
標高が1600mを越える茶畑ゆえに生産量が少なく、高級な茶になっています。
近年は茶区内の龍鳳峡産茶が注目され、人気です。
製茶された茶葉は、他の高山茶と比べるとやや緑がかっています。
味は、台湾高山茶独特の甘みと渋みがある茶だと思います。
ちなみに、中国語では濃く淹れた茶を 「苦茶」 と言いますが、
茶の味を渋いとは表現していませんでした。
最近になって、茶の味を表現するのに 「渋」 も使われるようになってきましたが、
それは日本で言う渋みと少し違います。
中国語でも熟していないフルーツを食べたときに「渋」と表現することがあります。
茶の味にフルーツの渋みに通じるものが感じられるときに使います。
ただし、悪い意味ではなく、フルーツのように清々しいということを表現しています。
台湾大地震では杉林溪も大きな被害を被りました。
観光地 「杉林溪遊楽区」 では道路が寸断され、復旧に4年間もかかりました。
そんな中、杉林渓茶区内では台湾大地震後の町興しとして、
茶農の方々が自主的にひとつの試みとして緑茶生産に取り組みました。
台湾では、緑茶は輸出用か、特別な注文がなければ生産しないと言ってよいほど、
あまり馴染みのない茶でした。
しかし、杉林渓緑茶は珍しさもあってか結構評判になり、生産が本格化してきました。
特に、海抜の高い茶畑で採取されたものは杉林渓高冷緑茶として商品化されています。
今後の発展を期待したいです。
楊品瑜 2004.11.26 (転載不可)
|
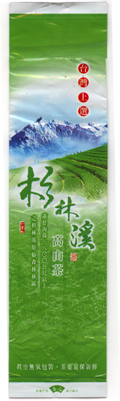
杉林渓高山茶
|
|

|
|

