天鶴茶は花蓮県瑞穂郷舞鶴の茶です。今でも思い出深い高校二年生の冬、父が一足先に日本に赴任し、
翌年からは家族全員の日本への引越しも決まり、家族が揃ってでかけた最後の旅行が、
台中から太魯閣峡谷経由の花蓮への旅行でした。
台風のつめ跡が深く、結構危険な公共バスを使っての旅でした。
当時は茶に関する仕事をするとは思っていなかったので、
残念なことに茶に関する記憶は、
駅や屋台のあちらこちらでバケツに入れて売られていた、八角の匂いがプンプンする茶葉蛋ぐらいです。
明の時代にポルトガル人が台湾東海岸の花蓮あたりに到達した時に砂金を発見し、
「哆囉滿」と名付けました。
台湾に清朝の実権が及んでからは、花蓮県の瑞穂郷あたりは、咸豐四年に卑南廳に、
そして後の同治元年には台東州に属しました。
このときに、清兵が駐在した「水尾」より開拓が始まったとされています。
日本統治時代に日本政府は、台湾地名を日本とゆかりのある地名に変えましたが、
「水尾」も日本神話の「豊葦原の瑞穗国」にちなんで「瑞穂」と改名されました。
戦後は賛否両論ありましたが、
既に慣れ親しまれていたために多くの地名がそのまま使われています。
花蓮県瑞穂郷もそのひとつで、ここの舞鶴台地には舞鶴観光茶園があります。
また、温泉や掃叭遺跡の舞鶴石柱などの史蹟もあり、人気の観光地になっています。
日本統治時代は茶のほかに、コーヒーの栽培が行われていました。
コーヒーはアラビカ種が主で、台南県東山、雲林県古坑、花蓮県舞鶴が三大産地だったそうです。
農地として本格的な開発が行われたのは、民國五十二年(1963年)頃、
彰化芬園郷の鳳梨(パイナップル)農家が舞鶴台地に移住し,
コーヒー栽培を行うようになってからです。
舞鶴では地質が茶栽培に適していたこともあり、
民國六十二年(1973年)に台湾省茶葉改良場の指導により、
舞鶴台地に適した茶樹に改良され、茶農家が多くなりました。
現在は金萱、翠玉、青心烏龍、大葉烏龍などの品種が栽培されています。
舞鶴で生産される茶は天鶴茶と呼ばれています。
その名は、戦後茶園開発にもっとも貢献した銭天鶴博士を記念して命名されたというのが
最もポピュラーです。
味は渋みがあまりなく、やや甘みのある伝統的な烏龍茶の味です。
茶湯の色は日本でよく売られている烏龍茶のような茶褐色です。
この文章を書くために、久しぶりに飲んだのですが、懐かしい味でした。
台湾ではめずらしい取り組みとして、花蓮県政府による天鶴茶を使ったアイスティーの普及活動があります。
もともと台湾ではアイスティーを飲む習慣が無かったのですが、
泡抹紅茶や英国紅茶の影響を受け、台湾人にも徐々に受け入れられてきています。
一般的に夏茶は苦く渋いため商品としては人気がないのですが、
舞鶴ではアイスティー用に夏茶の茶摘みを増やしています。
天鶴茶を使った食品開発も多く行われ、羊羹や茶菓子などを作り、お土産品として多く売られています。
また、欖仁茶も名産品のひとつになっています。
これは欖仁(中国オリーブの実)、桑の葉、茶葉のブレンド茶です。
楊品瑜 2004.12.02 (転載不可)
|
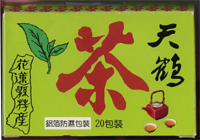
天鶴茶(ティーバッグ)
|
|

|
|

