台北県三峡鎮は、陶器の街 鶯歌鎮 の隣町に位置し、老街が多くレトロな街として人気の観光地です。
三峡の地名は大漢溪(河)、橫溪、三角湧溪の
三つの川から作られた扇形の平原に位置していることに由来するとされていますが、
三つの川の合流点が三角の波を起こすことから名づけられたとの説もあります。
日本統治時代に「三角湧」の音が日本語の「三峡」に近いことから、「三峡」という地名になったのです。
最初の開拓は、明朝末期に淡水河に沿って入港した漢民族が住み着いてからとされています。
清の同治3年(1864)、イギリス商人のジョン・ドットが台湾(南投県魚池一帯と推測されています)での自生茶樹を発見し、
1866年には福建省安渓から茶の苗を移植し、この地方および文山堡に茶樹の栽培を奨励し、
茶の栽培がさらに盛んになりました。
栽培された茶は船積され、淡水河に沿って大稲埕に運ばれ、洋行(西洋資本の貿易会社)によって海外に輸出されました。
ドットは、通訳を担当した李春生と共に、1869年にニューヨークに烏龍茶を輸出しFormosa Tea(台湾茶)を有名にした人物です。
また、李春生はドットの後を引き継ぎ、洋行の代表となり、「台湾茶の父」とも呼ばれています。
三峡において初期に試みられたのは紅茶でしたが、品質が悪いものでした。
日本統治時代に入ってから、主に烏龍茶と包種茶を栽培するようになりました。
当時の行政区分は台北州海山郡三峡庄で、この辺りの茶は海山茶とも呼ばれました。
日本統治時代から日本向けに緑茶も作られるようになり、龍井茶と碧螺春茶が生産されるようになりました。
そして、近年では、台湾緑茶の代表的な産地となっています。
日本統治時代の海山茶の様子は、1924年9月の台湾日日新報に「海山茶の名声を挙よ」という記事に見ることができます。
三峡庄において製茶品評会が開かれ、この様子が紹介されています。
その中では三峡が海山郡で一番の茶産地であったこと、
現在は茶産地という印象がない隣町の鶯歌が三峡に次ぐ産地だったことが分かります。
三峡茶区は西南区の弘道里、五寮、大埔、金敏、插角、有木と
東北区の礁溪、白雞、溪南、溪北、成福、安坑、竹崙に分かれて栽培されてきました。
西南区は文山茶区と隣接しています。
茶樹品種は主に青心柑仔が栽培されており、現在は主に龍井茶が生産されています。
上等な龍井茶は一芯二葉で茶摘みを行います。
茶の特徴は香り高く、茶湯は澄み、明瞭とされ、味はやや苦味(日本的には渋み)はありますが、
喉越し時には甘みに感じます。
三峡産の龍井茶、碧螺春茶は、中国産に比べ葉が大きいのが特徴です。
もちろん、味や香りは似ています。
良質な中国産龍井茶の葉も大きいので、一般の人には龍井茶は見分けにくいかもしれません。
碧螺春茶は、台湾茶の方がねじりがゆるくなっており、見分けることができると思います。
楊品瑜 2005.03.16 (転載不可)
|
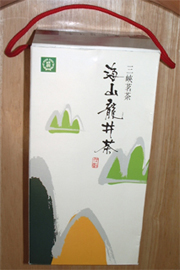
三峡茗茶 海山龍井茶
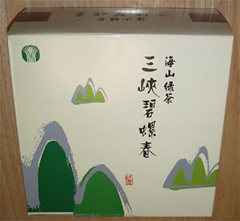
海山緑茶 三峡碧螺春
|
|

|
|

