ここで紹介する台南県白河鎮産の蓮花茶は、茶葉に蓮の花の香りを付けたものではなく、
蓮の花を乾燥して茶外茶として飲まれている茶です。
白河の地名は急水渓の支流である白水渓の北岸にあることに由来します。
その開発は古く、明の時代に泉州人によって行われ、農産品の交易口として栄えたことで、
台湾語で「店仔口」(店先の意味)と呼ばれていました。
日本統治時代の大正9年(1920)に白河庄と改名され、今日に至っています。
また、日本統治時代に開発が行われた人気の温泉地「関子嶺」があることでも有名です。
台湾台南県白河鎮の蓮は、100年ぐらい前に日本から優良な品種や種子を取り寄せたのが始まりだそうです。
北五里に多く栽培されていましたが、栽培が盛んになったのはここ数十年です。
主に大賀蓮・建蓮・石蓮が栽培されています。
大賀蓮は、1951年に大賀一郎博士が千葉県検見川の地下地層から発見した二千年前の数粒の蓮の種子から育てられた古代蓮で、
1970年代に台湾にも植えられました。
台湾では大賀の語音から「大憨蓮」とも呼ばれています。
白河鎮では6月から蓮の花が咲き始めますが、蓮の花の開花状況に合わせて7月か8月に白河蓮花節(祭り)を行っています。
蓮花茶や蓮根料理など蓮づくしが楽しめます。
また、近年は茶園と提携して觀賞茶園も試みられています。
台湾人の習慣として蓮の実はさまざまな料理、デザート、菓子に使っています。
蓮根は蓮藕と呼び、粉にして茶、料理や菓子に使っています。
バリエーションが非常に多いですが、日本でよく食べられているように蓮根をそのままスライスして使うことは比較的少ないようです。
ただ、正月料理のスープで厚さ1センチほどに切ったレンコンを豚のスペアリブ、ピーナッツで煮込んだスープは有名です。
このスープを正月に飲むことには諸説ありますが、
「年年有余」や「連年有余」(毎年余りますように)という縁起の良い言葉が「蓮年有余」につながっているという説があります。
「蓮花」は漢方薬としても分野が確立され、気分を鎮めたり、体調を整えるなどの効果があるとされています。
白河鎮の蓮花茶は主に、つぼみを一輪ずつ乾燥し、数輪をセットにして販売されています。
蓮の花は種類によって開花と凋む時間が違うため、摘むタイミングは農家によって違うようです。
淹れ方は、800cc ほどのお湯に蓮花茶の一輪を入れて1分ほど待ったところで、湯のみに注ぎ分けるだけです。
蓮花のさわやかな香りとほのかな甘みが楽しめます。
白河蓮花茶の成功が引き金になって、茶業改良場台東分場では茶葉と蓮花をブレンドした『水蓮花茶』を発売しています。
また、白河鎮以外では桃園県観音郷も有名です。
最後に、古人の優雅な蓮花茶の楽しみ方を紹介しておきましょう。
明の時代の顧元慶の『茶譜』(1541年)によると、早朝蓮の花が開き始めたときに茶葉を入れ、翌日再度花が開いたときに、
茶葉を取り出し、乾燥して蓮花茶にしていたそうです。
楊品瑜 2005.05.24 (転載不可)
|
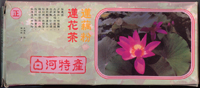
白河蓮花茶
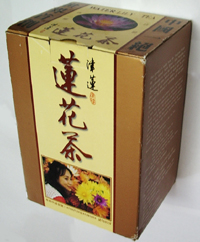
大賀蓮の蓮花茶
|
|

|
|

