峨眉郷は新竹県の最南端に位置し、地形は標高がほぼ500メートルの竹東丘陵の南端と獅頭山の丘陵地です。
郷の南端は苗栗県三湾郷と、西は新竹市と隣接しており、新竹科学園区の後花園(裏庭)とも呼ばれるそうです。
峨眉はかつて月眉と呼ばれ、名の由来は峨眉溪の一部が半月形で眉に例えられたのが名の由来です。
古くは原住民賽夏族の居住地でしたが、1834年頃から客家人の集落として開拓が始められ、
日本統治時代の大正9年(1920)に総督府により峨眉と名を変えられました。
一帯の山は高温多湿で、霧が多く、茶栽培に適した地形と気候として、古くから茶栽培が行なわれてきました。
また、峨眉湖(別名大浦水庫)や仏教の聖地である獅頭山(苗栗県南庄郷との境界)、六寮古道、牛車路古道、
環湖歩道、藤坪歩道、十二寮歩道、峨眉富興阿良頭樟脳寮、富興老茶工廠など多くの観光地があることで知られいます。
樟脳寮では樟脳油を生産し、火薬や化学原料として、台湾経済の初期の重要産品でした。
富興村の富興百年茶廠は130年の歴史を持つ粗茶工場で、紅茶を主力に生産し、
欧州と北アフリカに輸出していました。
このため一般には紅茶工場と呼ばれることが多かったようです。
台湾の紅茶産業の衰退を受け、1970年代からは経営が悪化し、残念なことに1991年に閉鎖されました。
製茶機具などの設備はまだ残されており、茶葉博物館となるように検討されているそうです。
近年、富興村一帯は茶工場を中心に老街として観光地になるように整備しました。
一方で獅頭山と峨嵋湖風景区では1997年に茶農家の協力で富興茶葉展示中心が作られ、
製茶区、泡茶(茶の淹れ方)区、展示区と三部分に分れて、茶を楽しむことができます。
入り口は、仙女のような中国古代美女が急須を持って歓待している像が目印になっています。
また、定期的に茶のコンクールが開催されています。
峨眉郷産の東方美人茶は、隣りの北埔郷と並んで高価です。
芒種期(6月頃)前後に小綠葉蝉または浮塵子と呼ばれる日本語訳ではウンカに茶葉を噛ませ、自然発酵を発生させることで、
旧暦5月5日の端午節の前後十日に一心二葉で茶摘みした茶葉が、特有の香と味が生じると言われています。
茶摘みは原則年に一回です。
ウンカに茶葉を噛ませる製法は無農薬ということなので、味や香りだけでなく、これも人気要因になっています。
ただし、茶農家は「嫁が来ない」と嘆くほど、虫との戦いの日々なのだそうです。
湖光村の十二寮休閒農業区でも野菜の他、東方美人茶や峨眉包種茶、烏龍茶、金萱茶、翠玉茶、
四季春の製造過程が見学できます。
茶焗蛋(茶葉を使用した燻製卵)が名産品で、土産店などで食べることができます。
近年の台湾産東方美人茶は、白毛猴種茶樹で作ったものがもっとも高価とされています。
台北県坪林郷で実験的に栽培されたのが高い評価を得ているのです。
しかし、生産量がまだまだ少ないです。
白毛猴種はもともと台北県三峽鎮、坪林郷、宜蘭県、新竹県、苗栗県一帯で少し栽培されていましたが、
茶葉は小さいため包種茶、烏龍茶作りに不適とされていました。
このため、東方美人茶向けに改良され、東方美人茶に最適な茶樹と評判になっています。
峨眉郷と北埔郷でもこの品種の栽培を増やしており、今後が大変注目されています。
楊品瑜 2007.08.01 (転載不可)
|
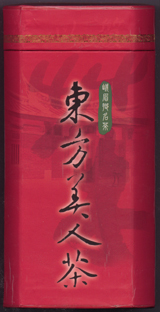
峨眉郷銘茶 東方美人茶
|
|

|
|

