竒莱山(きらいざん)は台湾中部の南投、台中、花蓮三県に跨ぎ、最高峰は海抜3607メートルに及びます。
茶区は南投縣仁愛郷の海抜2000メートル辺りにあります。
また、台湾は亜熱帯気候に属しますが、竒莱山の山頂に雪が積もることもあります。
日照が短く、霧が多く、平均気温も比較的に低いため、茶葉の生長が緩やかなため、
厚みのある茶葉となり、平地で栽培された茶葉より渋みが少ないとされています。
一方で、茶区の開発が遅かったため、栽培環境がよく、土壌の栄養価も高いとして、
高級茶葉が採取できる新興茶区であります。
仁愛郷は、主に原住民のアタイアル(Atayal、泰雅族)、サイセット(Saisiyat、賽夏族)、
ブヌム(Bunun 、布農族)の居住地です。旧「霧社」の地です。
日本統治時代は、台中州能高郡の蕃地(原住民の居住地)に属し、
戦後1946年4月1日に能高郷と改名、台中県能高区に属していました。
1950年10月に南投県に編入され、現在に至っています。
仁愛郷には1950年、タイとミャンマーの国境地帯から撤退した国民政府軍とその家族の移住を受け入れ、
新しい村が形成されています。
雲南擺夷文化(雲南傣族、俗称擺夷族の子孫)が郷の特色となっています。
仁愛郷の行政中心地である霧社は、日本統治時代に於いて、
国内外を震撼させた所謂「霧社事件」が起きた場所です。
しかし、現在は郷全体が「桜の都」として、人気の観光地になっています。
実は台湾では、竒莱山を登らなければ、真の山男、山女として認められないほど、
竒莱山は登山家に大変愛されている山でもあります。
しかし、登山に人気の山である一方、「黒色竒莱」とも呼ばれています。
由来は、竒莱山は日本統治時代から幾つかの多人数が参加した登山隊の遭難事故が発生した山であったからです。
その理由は西側が傾斜し、太陽を背にしているため、昼過ぎになると山全体が早くから暗くなります。
加えて、濃い霧が出やすく、視界を遮り、山の気候が急変すると、道に迷いやすくなると言われています。
険しい高山の茶区で育った茶葉ではありますが、
飲んだ感想としましては、香り高く、まろやかなお茶でした。
台湾産高山茶全般に言えることですが、台湾では平地でも一般に優れた茶の栽培が出来ます。
あえてより環境の優れた高い山で、新規に茶園を開拓し、台風も頻繁に来るリスクがあるなか、
決して楽ではない茶栽培を一生懸命に栽培し、提供してくれている茶農家のご苦労に感謝します。
そして、竒莱山茶の生産量はまだ、少ないようです。
なので、より大事に飲みたいお茶のひとつでもあります。
楊品瑜 2013.06.20 (転載不可)
|
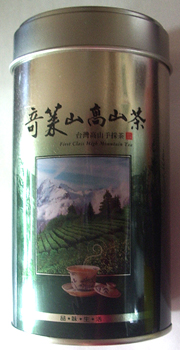
竒莱山高山茶
|
|

|
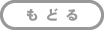 |
|

