梅州市は広東省の東北部に位置し、北部は江西省、東部は福建省と隣接しています。
原住民彙族(イー族)と豐順県の一部に漢民族の潮汕人が住んでいますが、客家人が最も多く住んでいます。
城南を流れる梅江によって潮州、汕頭とむすばれ、中流と上流の貨物はほとんどここに集散されます。
漢代は掲陽県、晋代は梅陽県の属地でしたが、南斉(中国の南北朝時代に江南に存在した国)になって、
ここに程郷県が創設され、これが明代まで続きました。
その間、南漢は敬州を置きましたが、北宋の開宝4年(971年)に梅州と改められました。
元も梅州路を置き、軍隊を派遣して梅州に進攻し、彙族を鎮圧した歴史があります。
明初、梅州路が廃止され、清朝は程郷県を嘉応州としましたが、
民国に入って梅県と改められました(アジア歴史事典第7巻参照)。
このように梅州は紆余曲折の歴史を経て、現在は「世界客都」となり、
世界中の客家人の中心都市として位置つけされています。
梅州の名の由来は、幾つかの説があります。
古くから沢山の美しい梅の木があったことからという説が一般的ですが、
『光緒嘉応州志』では梅州には「梅峰山」、「梅溪水」と呼ばれる地名があったからだとの記載もあります。
名農産品についていえば、茶業は、主力産業の一つであり、
「中国単欉茶之郷」(中国単欉茶の郷)としても有名です。
単欉(叢も使われていますが、本来中国語では欉は一本ずつの木、叢は草むらの意味があります)とは、
元々一株ずつから茶葉を採取し、選定し茶作りをしたことに由来します。
近年では単欉に産地などのブランド名がつくようになり、多くの人気単欉茶が誕生しています。
茶業の発展とともに、2009年の6月4日には梅州市東部の大埔県茶陽鎮に於いて、
関羽(三国の時代)と岳飛(南宋の時代)は忠義の化身として、
60年間停止した「関岳出巡」(関羽と岳飛が巡行に出る)の収穫祭が大規模に行われました。
因みに中国の多くの宗教は多神教なので、時代が違っても一緒に祭られることがあります。
大浦県は現在でも多くの土楼が残されています
(ちなみに、土楼は福建、江西、広東三省の境に多くあり、随意談第43号 と 聊天話茶 でも紹介しています)。
また、茶陽鎮は竹林が豊富で、鎮の歴史としては、隋の時代から開拓はあったようですが、
明の代時代に県となり、潮州や汀洲の管轄を経て現在は梅州市の管轄となったそうです。
関連性ははっきりしませんが、中国南部では工夫茶器で急須を茶船の縁に沿って回す、
「関公(関羽)巡城」の習慣が広く行われていました。
現在は茶器を傷めるということで控えるようになりましたが、ずっと由来がはっきりしませんでした。
幾分か客家文化の影響が推移されますが、福建人を中心に媽祖信仰も多いなか、
多くの茶飲みには関公とのかかわりが、精神面ないし文化面と切り離せない存在のようです!
また、茶海(濾した茶湯入れ)から茶杯に茶を注ぎ分けることを「韓信(漢初の武将)点兵(点呼)」と呼ぶことがあります。
入手した梅州茶は、茶農家が自分たちで気軽に飲むための半発酵の荒茶ですので、
見た目からは商品価値としてはどうかと思うほど雑な仕上がりとなっています。
しかし、味と香りはともに良く、茶葉特有の蜂蜜の甘みも程よく味わえます。
このお茶を飲んでいると、茶はただ、飲めばよいのだとの錯覚に陥りそうですが、
梅州の歴史を感じて飲むとやはり、一段とお茶の有難味を感じました。
楊品瑜 2010.01.10 (転載不可)
|

英師名茶
|
|
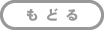 |
|

